一般質問
○議長(菅原琢哉) 日程第1一般質問を行います。
通告により順次質問を許します。
─────────────────────
○議長(菅原琢哉) 若松尚利さん。
【6番 若松尚利議員 登壇】
◆6番(若松尚利) 会派そうせいと維新、日本維新の会の若松尚利です。皆様からこの議員という立場をお預かりして、1年と少しがたちました。会派の先輩や同僚議員にも恵まれ、また他会派の皆さんにもよくしていただき、議会の歩き方をようやく覚えたところです。せっかくお預かりしたこの立場、伝統を尊重しつつも、新しい視点からの新しい取組にも少しずつ取り組んでいきたいと思います。年に1度しかない一般質問の機会。今回もたくさんの質問をさせていただきます。穂積市長に一般質問する機会は、市長の今任期中では最後となります。せっかくの最後の機会ですから、聞きにくいことも聞かせていただければと思います。
それでは、通告に従い質問させていただきます。
1、市長の政治姿勢について。
(1)外旭川地区のまちづくりにおいては、都市計画法上、商業施設等を建設することができない土地にもかかわらず、地域未来投資促進法の活用を検討するなど、かなり思い切った手法での整備を目指しているが、これと同じ熱量で臨めば、これまで各議員が提案し、予算や制度の面で困難とされた事業も実現可能と考えるがどうか。
(2)今年2月の知事の発言にもあったとおり、外旭川地区のまちづくりについて民意を問う必要はないのか。また、仮に民意によって同まちづくりの推進が決まった場合は、どのようにして土地利用制限の課題を解決するつもりなのか。
(3)本市においては、他自治体に先駆けた新しい取組が少ないように感じるが、市長の評価はどうか。また、あまり挑戦しないのは庁内の風潮もあると思うが、その風潮は、市長が影響を与えている可能性はないか。
(4)一議員では実現が難しいことも首長であれば実現可能であることが多いが、市長が今、実現したいと強く思っていることは何か。
首長の思いでまちが大きく変化していったさまを、私たちはいろいろな地域で見ることができています。ぜひ、穂積市長が残りの任期で、あるいは次の任期があるとするならばその任期の中で、これを実現しなければ死んでも死に切れないというものがスタジアムのほかにもあるのならばお聞かせいただきたいです。
(5)万博首長連合に加盟していないが、加盟する考えはないか。また、市長は万博反対の立場なのか。さらに、加盟している横手市が大阪・関西万博において、かまくらの展示を行うが、本市においては、万博というPRの好機を生かす取組は行わないのか。
2025年、大阪・関西万博の開催を契機とした地域の未来社会を創造する全国の自治体のネットワーク、2025年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を創造する首長連合に秋田市は加盟しておりません。東北の県庁所在地では、青森市、山形市、盛岡市が、県内では、横手市、男鹿市、湯沢市、由利本荘市、北秋田市、にかほ市、羽後町、上小阿仁村、大潟村が加盟しております。秋田市は加盟しないことに何か理由があるのでしょうか。また、先頃、東北絆まつりで、秋田竿燈まつりを含む東北の祭りが大阪・関西万博で披露されることが発表されましたが、会場内のEXPOホールやEXPOメッセで自治体が展示やイベントを開催する例は数多くあります。秋田市は独自の展示などを行わないのでしょうか。県と共に、秋田の観光誘客だけでなく、企業誘致や移住の促進に向けたPRを行うべきと考えますが、市のお考えをお聞かせください。
2、外旭川地区のまちづくりについて。
(1)新スタジアムを八橋地区に整備する場合、卸売市場の工期短縮の必要性が薄れるが、工期や工程は変更しないのか。また、卸売市場の位置を現在地から移動させ、商業施設を土地利用の制限が少ない現在の卸売市場敷地に整備するなど、同まちづくり全体を見直す考えはないか。
もちろん、市場の工期短縮はスタジアムのためではないということは分かっております。間もなく花き棟の設計が始まる局面ではありますが、市場の建設地を横山金足線沿いに移動させてしまえば、ローリングも不要となります。例えば、市場と食品加工業者や流通業者、観光農園、産直施設などを複合的に配置した施設であれば、地域未来投資促進法の趣旨にも沿った施設となるのではないでしょうか。そして、商業施設も現市場用地に造れば土地利用の制限の問題もないと思うのですが、いかがでしょうか。
(2)同まちづくりにおける市の負担総額は幾らと想定しているのか。
(3)外旭川地区まちづくり事業パートナー選定プロポーザルは出来レースだったのではないかとの意見があるが、その意見をどのように受け止めているのか。また、結果的に提案者3の提案内容に近づいていったが、その点についてどう考えているのか。さらに、これらの点を踏まえ、今後、市で行う事業者選定プロポーザルに生かせる教訓は何か。
事業者選定プロポーザルに当たっては、事前に寄せられた質問の中で、出来レースと思われないようにとくぎを刺されておりました。また、市民からもそのような声を聞くことがあります。個人的には、提案者3のAKITA GREEN GARDEN CITYのほうが結果的によかったのではないかと思いますが、過ぎたことは仕方がありません。今回のことからぜひ教訓を得ていただきたいと思います。
3、新スタジアム整備等について。
(1)民設民営を前提に進めているが現実的に可能なのか。また、整備費の3分の2を公費で負担する計画は民設と言えるのか。さらに、今後、他の民間施設整備を行う際に、整備費の3分の2を公費で負担することはあるのか。
(2)八橋地区に整備する場合、八橋運動公園内の既存施設を統合するなどのコスト削減策を実施し、公設公営で整備する考えはないか。また、同地区に整備する上での課題とその解決策はどうか。
(3)新スタジアムの維持管理に係る赤字を市が負担する可能性はあるのか。また、市が負担する場合には、どのような条件で、どの程度の金額までなら許容されると考えているのか。
現在、八橋地区には、陸上競技場を含めると、天然芝3面、人工芝1面の計4面のサッカーができる場所があります。これらを例えば天然芝2面、人工芝1面に統合することは、少子化、人口減下では可能なのではないでしょうか。また、現在のASPスタジアムを大規模改修する、あるいは新しくスタジアムを造るのならば、ASPスタジアムのスタンドや建物部分を撤去する、人工芝化するなどして、今後の維持費を抑えつつ、ラグビーやアマチュアにも使わせる、プロのための芝生の養生期間も使用料を徴収するなど一定の公共性・公平性があれば、新スタジアムが公設公営であってもある程度の理解を得られると考えるがどうでしょうか。
4、子どもたちの笑顔が輝く秋田市へ。
秋田市は、消滅可能性自治体こそ免れたものの、例えば人口当たりの出生数で出雲市と比べると大きく見劣っている状況です。単純な出生数で言えば、出雲市は約17万人の人口で1,302人もの出生があります。規模感が近い高知市は約32万人で2,006人、お隣山形市も約24万人に対して1,603人です。秋田市は約30万人で1,589人しかいません。これは一体どういうことなのでしょうか。
(1)合計特殊出生率において、他の中核市や県庁所在地と比べて低い水準にあるのは、これまで実施してきた少子化対策がほとんど効果がないことの現れとも考えられるが、子どもを産み育てたいと思えるまちにするため、今後、どのように取り組んでいくのか。
(2)全国学力・学習状況調査において、秋田県は良好水準とされているものの、難関大学への進学者数、卒業後に秋田市に残る若者の数、秋田市での起業者数など様々な評価指標もあると考えるが、現在の本市の学校教育をどう評価しているのか。
生まれてきてくれた子どもたちを、無事に大人に育てるのが私たちの役目です。事故で命を落とす子どもを一人でも減らしたい。そんな思いから、新入学生に黄色い帽子ではなく黄色いヘルメットを配る学校、水の事故を防ぐためにライフジャケットを学校に配布し、学んでもらう地域などもあります。
そこでお尋ねいたします。
(3)事故に最も遭いやすいとされる「魔の7歳」対策にどのように取り組んでいるのか。また、通学用ヘルメットの無償配布、自転車用ヘルメット購入に対する補助金やライフジャケットの配布など、他自治体において子どもの事故対策を行っているが、本市で同様の取組を行う考えはないか。さらに、実施に向けた課題とその解決策はどうか。
先日、小学校の給食中に、子どもが鶉の卵を喉に詰まらせて亡くなるという痛ましい事故が他県でありました。もちろん給食の調理方法などに気を遣っていただくことは必要ですが、喉に詰まらせるのは食べ物だけとは限りません。窒息時、10分経過で死亡率が50%、15分経過で100%になるとされています。その場にいる担任の先生や保育士の力で救命率を上げることが必要です。
そこで、
(4)子どもの窒息事故対策にどのように取り組んでいるのか。また、各小・中学校、幼稚園や保育園への救急車の到着時間は把握しているのか。さらに、各小・中学校、幼稚園や保育園の職員向けに、窒息事故対応の実技訓練を最優先で行うべきではないか。
また、これも他県での事例ですが、救急隊が搬送不要とした3歳の男児が、その後、急性脳症と診断され、重度の知的障がいを負ったという事故がありました。事ほどさように子どもの救急対応は難しいのだと思います。
そこで、
(5)子どもの救急搬送を断ったケースはどの程度あったのか。また、その後の状況は調査しているのか。さらに、日本臨床救急医学会小児救急委員会が開催している救急隊員向けのトレーニングについて、本市の受講状況はどうか。
(6)本市において、子どもの一時預かり、デイケア、ショートステイ、病児・病後児保育及び学童クラブの一時利用は、働く保護者にとって利用しやすいものになっているのか。また、必要なときにすぐに利用できるように、市として取り組んでいくべきではないか。
もちろん、アレルギーの把握などの点で事前に申し込んでおくにこしたことはありませんが、やはり仕事や精神面で突発的に子どもを預けたいと思うことは、どうしてもあることだと思います。難しいとは思いますが、ぜひ子育て世代に寄り添って何ができるか考えていただきたいとともに、子育ての現場で働く職員の処遇改善にも取り組んでいただきたいです。
(7)保育士等や看護師等の奨学金返還助成について、令和7年度以降も継続する考えはないか。また、保育士等の対象施設に児童養護施設、母子生活支援施設及び乳児院も加えるべきと考えるがどうか。
5、公共交通等について。
(1)公共交通への積極的な関与について。
エリア交通は、セーフティーネットとして市が関わっていくのは福祉政策的にもよいことですが、企業誘致や都市機能の維持、そしてシティセールスの観点からも、鉄道、幹線系のバス、スムーズな移動のための渋滞緩和など、都市交通の視点も重要です。
そこで、
ア、都市交通について市が積極的に関与してはどうか。また、バスの利用率が低い理由は、夜間の便数が少ないなどの不便さにあるのではないか。
先日、秋田駅のバスターミナルに20時過ぎに行って愕然としました。人けはありません。県庁所在地のメインのバスターミナルなのに、20時15分以降のバスが8本しかないのです。飲んだ後やあきた芸術劇場ミルハスで何か見た後に使えるバスは、ほぼないということです。同じく民営のバスが主体の福島市では、乗員不足の中、やりくりをして22時台までの運行を意識して確保しているとのことでした。車に頼らない便利な移動の維持、実現に、市が産業面、観光面、文化振興面で主体的に取り組めないでしょうか。
イ、2050年のゼロカーボンシティの実現に向けて、公共交通分担率の目標値を定めるべきと考えるがどうか。また、交通分野において、カーボンニュートラルの実現に向けてどのように取り組んでいくのか。
1割が車から公共交通に乗り換えるだけで、渋滞は半減するとも言われています。ぜひ公共交通分担率の目標を掲げていただきたいです。
ウ、バス路線網の維持が困難となっているが、市営バスの移管に関し、間接移管方式ではなく民間移管方式を選択したことについての現在の評価はどうか。また、その際の「秋田市交通局の路線移管に関する基本協定書」を保存していない理由は何か。
当時の秋田中央交通社長の渡邉氏、市議の相場氏と当時の交通事業管理者が「我が町の営みを育みし赤バスよ 時至りて幕閉じるを淋し」といった短歌を読み合うという粋なやり取りの記録が残っていますが、当初決まりかけていた間接移管方式を選ばずに維持が困難となりつつある現状を、当時の人たちはどのように見るのでしょうか。
エ、第3次秋田市公共交通政策ビジョンで掲げた共同経営体の実現の検討状況はどうか。また、幹線バス路線の一部公営化やいわゆる旧80条バスの運行などを市で行う考えはないか。さらに、その実現に向けた課題は何か。
オ、バス運転士が不足しているため、公共交通の自動運転化が急務と考えるが、本市において比較的自動運転化しやすい鉄軌道系の公共交通を整備する考えはないか。また、市内のJR線路を利用し、バッテリートラムなどのLRVを混走させ、各踏切ごとに停留所を設けることで、比較的安価に鉄軌道系の公共交通が実現できると思うが、実現に向けて研究する考えはないか。
既存のJR線路にLRT車両、LRVを走らせた事例は富山市でありますが、LRTに完全転換せず、廃線となったJR線路を間借りして走らせた事例はありません。泉外旭川駅は地域の人が便利に使っていますが、いかんせん建設費が高くつきました。それがLRVが止まるだけの停留所を踏切付近に造るだけなら、相当安くできます。想像してみてください。秋田東中学校近くの踏切、秋田工業高校の裏の踏切、自衛隊前の踏切、そういったところで乗り降りできたら。JRも地方部におけるローカル輸送をどう維持するか悩んでいると思います。ぜひ他都市に先駆けて研究していただきたいです。ミニ新幹線も、秋田県で研究検討している間に山形県に先を越された過去があります。そして、バス、鉄軌道系だけではなく、改正地域公共交通活性化再生法ではタクシーも公共交通として位置づけられています。
そこで、
カ、タクシー事業者に対して、運転免許返納者に対するタクシー運賃割引分を補助する考えはないか。
キ、バスやタクシーの運転手不足が深刻であるが、募集活動への補助だけではなく、旧秋田市交通局の職員の派遣や第二種運転免許の取得費用及び給与の補助など、直接的な支援を行う考えはないか。
他都市では直接的な支援が行われています。お隣岩手県でも行われていますが、このままでは秋田で育てた運転手が、ほかの地域に流出することにもつながりかねません。
(2)バス路線網の再編及びエリア交通について。
これらは、バスを使うほどではない輸送量の路線を置き換え、既存のバス停にこだわらないよい取組かと思います。一方で、まだ検討段階ですが、不便なようにも見えます。乗り継ぎをするのも、都会のように10分、20分待てば次の電車やバスが来るところならよいですが、1本逃すと数時間待つようなことになるのが現在の秋田市です。
ア、市の再編路線網(案)では乗換時間が短く、遅延によって乗り継ぎできない可能性があることに加え、大学病院の外来受付や面会を行っていない時間帯にバスの運行を予定しているなど、利用者の実態に即していない面が見られるが、路線網の再編は適切に行われていると考えているのか。
例えば、免許センターには日中にバスで行けなくなりそうですが、本当にそれでよいのでしょうか。
また、エリア交通は、料金が高過ぎます。夫婦2人で買物に行くと片道600円、もし子どもと一緒ならと考えるとタクシー利用が視野に入ってきます。ましてシニアアキカの利用者ならどうでしょうか。
イ、エリア交通において1日乗車券や回数券を導入する考えはないか。また、交通系ICカードを利用可能とするため、タクシー事業者への補助を早急に行うべきではないか。
(3)自家用車等の利用について。
ア、2050年のゼロカーボンシティの実現に向けて、市有施設にEV用の急速充電ステーション及び燃料電池車や水素自動車用の水素ステーションを整備すべきではないか。
急速充電器の設置場所には、道の駅も考えられます。私自身も、様々な地域で道の駅にある充電器を利用してきました。今のところ、秋田市唯一の道の駅、セリオンの道の駅あきた港には、充電器がありません。しかし、そもそもの話として、道の駅としてあそこは利用しづらいと思いませんか。もともと道の駅として造られていない施設なので当然と言えば当然ですが。
そこで、
イ、道の駅あきた港は大型自動車用の駐車場が少ないなど、道の駅として利用しづらいことから、秋田臨海鉄道跡地を活用するため、土地所有者に働きかける考えはないか。
6、災害対策・危機管理について。
(1)広報監の新設は考えていないとのことであるが、本市において広報監は本当に必要ないのか。また、広報監がいなくても昨年の大雨災害において市民向けに十分な情報発信が行われたと考えているのか。
災害時において広報は重要と考え、広報監の新設を以前提案しました。秋田県庁では既に危機管理監兼広報監としています。また、戦略広報監を民間から採用している事例もあります。
(2)令和6年能登半島地震を踏まえた対応について。
年初の能登半島地震は被害が甚大で、いまだに復興も始まったばかりという状況です。昨年の大雨被害で各都市から助けてもらった秋田市も、積極的な支援に回っていただきたいです。
ア、本市からの応援職員の派遣状況はどうか。また、応援職員のフィードバックから本市の災害対応に生かすことのできるものはあったのか。
イ、耐震水道管等の継ぎ手での被害があったが、本市における対策状況はどうか。
ウ、大規模地震や繰り返す余震に対して、本市の防災における弱点をどう認識しているのか。また、その対策はどう行っていくのか。
(3)自主避難所への物資の提供は適切に行われるのか。また、在宅避難者に対してどのように対応するのか。
以前、奈良議員からの質問もありましたが、秋田市においては、他市にあるような市の施設などからスピーカーで放送する形の防災無線放送は行われておりません。私もこれは必要ではないかと考えますので、少し違った方向から確認してみたいと思います。
(4)屋外スピーカーを備えた防災無線の設置については、考えていないとのことであるが、他国からの武力攻撃時などにも備えて整備すべきではないか。また、整備するために国などの補助金は活用できないのか。
7、まちづくりと地域の活性化について。
秋田市の都市内地域分権の考え方は、非常に先進的であったと思います。これに立地適正化計画を組み合わせると、もっとよい形にできていたのではないかと思います。
そこで、
(1)秋田市立地適正化計画の策定から6年以上経過し、この間に市長の外旭川地区の開発への態度が変わるなどしているが、これまでの同計画の進捗状況をどう評価しているのか。また、地域自治区の検討もすべきではなかったのか。
(2)仲小路へのアーケードの整備は、地元商店街等が主体となって行うべきとのことであるが、整備に向けて市として関わっていくべきではないか。
小木田議員の代表質問でもありましたが、この種の施設はそもそも沿道の商店街や企業が整備するのが筋だというのは分かります。ですが、観光の拠点としても重要なエリアなかいち、そしてあきた芸術劇場ミルハスや秋田市文化創造館といった芸術文化ゾーンへのアクセスルートとも言えます。雨や雪を気にせず観光客が歩けるよう、市が主体的に関わってもよいのではないでしょうか。
(3)中心市街地の低未利用地を活用し、佐賀市で行われている「わいわい!!コンテナ」のような暫定利用の取組または暫定利用を促進する施策を行う考えはないか。
(4)呉市において、歩道を公園区域に変更して、電源と上下水道を整備し屋台を公募する取組が行われているが、同様の取組を中土橋などで行う考えはないか。また、実現に向けた課題とその解決策はどうか。
これらの取組は、一過性のイベントに頼らず中心部ににぎわいを取り戻す、他市の学ぶべき例と考えます。中土橋に限りません。広小路、中央通り、山王大通り、南大通りから御休み通りにかけてなどでもよいのです。
また、前回もお尋ねしましたが、
(5)中心市街地にマンションを建設する際、1階をテナントとするよう市として働きかけていくべきではないか。また、本市の顔ともいえる広小路において、テナントがないマンションの建設が進んでおり、建設地が50年程度商業地として使えなくなる現状をどう捉えているのか。
ぜひ市が積極的なまちづくりの方向性を示していただきたいと思います。
次に、県道から市道に移管された道路の沿道の市民から、秋田市になってから街路樹の管理が駄目になったという意見がありました。
(6)街路樹について、剪定方法などの管理状況や樹木の種類で市民サービスセンターごとに差があると感じるが、緑豊かな公園都市にふさわしい管理はできないのか。また、樹木の適正な管理やPRという観点から、公園課で担当すべきではないか。
泉ななかまど通りのナナカマドは、何回手を入れてもなかなか定着しません。これらは、市民サービスセンターの管理が行き届いていないことの現れではないでしょうか。他都市では、公園課が植樹ますの管理をしているところがあると聞きます。秋田市でもそういった取組はできないでしょうか。
(7)「これが秋田だ!食と芸能大祭典」について、これまでの開催をどう評価し、どのような波及効果があったと考えているのか。また、県外からの観光客向けのイベントにもかかわらず、県外からの集客はほとんどできてないと考えるがどうか。さらに、いつまで開催するつもりなのか。
今年の開催当日の新幹線、飛行機、ホテルの予約状況を見るに、県外からの集客はほとんどできていないように見えますが、イベントの内容と集客の実態の間にずれが生じていないでしょうか。もし県内客がほとんどであれば、県内のお祭りを何回も見せるより、県外・国外のお祭りを呼んだほうがよいのではないでしょうか。また、既存の飲食店に負の経済効果が発生してはいないのでしょうか。今後の市の関わり方も含めて検証、検討いただきたいです。
そして、何より大事なのが市民の安全安心な暮らしです。市民が抱える心配事を少しでも減らしていっていただきたいです。
8、安全安心な暮らしに向けて。
(1)北朝鮮による拉致問題について。
ア、映画「めぐみへの誓い」のDVDが市立中学校に寄贈されたが、活用状況はどうか。また、本市でも北朝鮮による拉致被害が疑われるケースがあるが、北朝鮮拉致問題に関しての学習はどのように行われているのか。
イ、ポートタワーセリオン等の市有施設において、北朝鮮人権侵害問題啓発週間に特別ライトアップを行う考えはないか。
(2)がん患者へのサポートについて。
ア、がん患者のウイッグ・乳房補正具の購入費用助成について、他自治体と比較し、本市の金額は十分と考えているのか。
イ、市としてヘアドネーションを促進する考えはないか。また、男性を含む市職員がヘアドネーションを行う上での課題はあるのか。
私自身も選挙に出る直前まで髪を伸ばし、規定の31センチメートルになったところで女性刑務所の和歌山刑務所内にある美容室に髪を送ったことがあります。この制度のよしあしもあるかと思いますが、市のお考えをお聞かせください。
そして熊の問題。特に勝平地区など熊の目撃情報が続く地域においては、住民は不安な日々を過ごし、また、子どもたちを学校に通わせることも心配かと思います。そういった地域においては、無人カメラの設置だけではなく、消防のドローンなども使い、熊の動向をつかんでいただきたいと思います。少なくても早朝に目撃があれば、学校に出かける前に各御家庭に連絡が行ってほしいと思います。
そこで、
(3)熊対策について、どのように取り組んでいるのか。また、登下校時における児童生徒の安全確保策はどうか。さらに、無人カメラやドローンなどで熊が確認された場合、秋田市公式LINEや防災ネットあきたメール配信システムなどで市民に速やかに周知してはどうか。
また、報道もあり、基準以下とはいえ、水道水と農薬についても不安を感じている市民は多いかと思います。
そこで、
(4)本市の水道水におけるネオニコチノイド系農薬の対策はどうなっているのか。また、雄物川上流地域の自治体と農薬の使用について協議する考えはないか。
同じく報道から市民が不安を感じているのは、生活保護費の返還についても同じではないでしょうか。既に受給している世帯はもちろん、いつ自分が働けなくなるか分からないのは誰もが同じだからです。
そこで、
(5)生活保護費における障害者加算の認定誤りについて、過支給分の返還を求めないことはできないのか。また、返還を求める場合にも、領収書などの証拠書類を紛失していても自立更生に資する費用を控除するなど、柔軟に対応すべきではないか。
長い長い質問も最後のほうになりました。とにかく議会に関心を持ってもらいたいというのが私の願いです。この長い質問群もその一つとなります。市民の皆さんが気になっていることに触れることができていれば幸いです。
9、市議会への関心を高める取組について。
(1)令和5年9月市議会定例会において、「他市の事例を注視しながら検討を進めてまいります」といった答弁は分かりにくいという趣旨の質問をしたが、その後の使用状況はどうか。また、そのような答弁をするのであれば、検討期間などを決めておくべきと考えるがどうか。
(2)他自治体で行われている議会答弁書の事前配付を本市でも行う考えはないか。また、実現に向けた課題とその解決策はどうか。
以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
答弁
○議長(菅原琢哉) 答弁を求めます。市長。
【穂積 志 市長 登壇】
◎市長(穂積志) 若松議員の御質問にお答え申し上げます。
最初に、1の市長の政治姿勢についての(1)外旭川地区のまちづくりと同じ熱量で臨めば、これまで困難とされた各議員の提案も実現可能と考えるがどうかについてであります。議員各位の提案は、市民の様々な思いを反映したものであり、本市の発展や市民生活の向上を目指す上で踏まえるべき視点であると認識しております。事業の採択に際しては、行政経営会議を通じて、社会情勢や市民ニーズ、事業の有効性などの観点から総合的に検討を行い、必要性を十分に精査しているところであります。また、事業の実施に当たっては、予算や職員といった経営資源を適切に配分するとともに、様々な制度の有効活用や関係機関との連携などを通じて、その推進を図っているものであります。
次に、(2)の外旭川地区まちづくりについて民意を問う必要性と、土地利用制限の課題解決についてであります。元気な秋田市と暮らしの豊かさを次世代に引き継いでいくため、前回の市長選挙において「未来が見えるまちづくりの促進」を公約に掲げ、多くの市民の皆様から負託を受けて、現在、官民連携によるモデル地区の整備に取り組んでいるところであります。今年度は、今年3月に策定した外旭川地区まちづくり基本計画において、内容の深掘りや見直しを行うこととしており、市議会等から御意見をいただきながら検討を進め、まずは現任期中において、このモデル地区整備に全力で取り組んでまいります。
次に、(3)の他自治体に先駆けた取組と庁内の風潮についてであります。本市では、これまでも未来志向で先進性のある取組を進めてまいりました。一例を挙げると、基本理念の一つに「まちづくりに貢献し、地域とともに歩む大学」を掲げる秋田公立美術大学を設置し、地場産業の振興や、秋田駅前をはじめ、まちなかの景観デザインなどに教員・学生が持つ専門性や創造性を生かすなど、大学と共に特色あるまちづくりを進めてきたところであります。また、企業版ふるさと納税を活用して実施したミラーライアーフィルムズプロジェクトにおいては、本市を舞台にした映画制作を通じて学生や若手クリエーターの新しい挑戦を後押しすることで、本市の未来をつくる人材の育成とシティプロモーションにつながっております。さらに、県と市が共同で整備したあきた芸術劇場ミルハスは、秋田市文化創造館と共に芸術文化ゾーンの核として、本市の中心市街地活性化に大きな役割を果たすとともに、公共施設の全体最適化や財政負担の軽減が図られ、全国に先駆けたモデルとなる取組とされているところであります。こうした取組を積み重ねており、今後とも私が先頭に立って、元気な秋田市を未来につなぐための施策を推進してまいります。
次に、(4)の実現したいと強く思っていることについてであります。本市総合計画に掲げる基本理念「ともにつくり ともに生きる 人・まち・くらし」は、市長に就任して以来変わらない本市の目指すべき姿であります。その実現に向け、洋上風力発電をはじめとする新エネルギー産業への取組や、官民連携による将来を見据えたまちづくりのモデルとなる取組を進めるなど、人口減少下にあっても持続可能な社会基盤の構築や、交流人口の拡大による新しい活力の創出と魅力づくりに取り組んでいるところであります。
以下の御質問につきましては、担当部局長より答弁いたします。
○議長(菅原琢哉) 企画財政部長。
【齋藤一洋 企画財政部長 登壇】
◎企画財政部長(齋藤一洋) 1の(5)万博に対する本市の考え方についてお答えいたします。今月8日に、東北6市で構成される東北絆まつり実行委員会において、来年度の大阪・関西万博への出展が正式に決定し、本市の秋田竿燈まつりについても、国内外に向けた大きなPRの機会を得ることができたと考えております。本市としては首長連合への加盟は考えておりませんが、加盟の要否にかかわらず、万博を応援する姿勢に変わりはないものであります。
次に、2の外旭川地区のまちづくりについての(2)市の負担総額についてであります。今年3月に策定した外旭川地区まちづくり基本計画において、想定される本市の負担として、卸売市場再整備に係る経費約115億円及び新スタジアム整備費の約30億円をお示ししたところであります。民間施設については、民間事業者が整備主体となり費用負担することを想定しており、地域未来基本計画の国同意後に、より具体的な内容を検討する中で、公共性の程度に応じ、本市の財政負担の在り方についても精査していくことになると考えております。
次に、(3)のまちづくり事業パートナー選定プロポーザルについてであります。同プロポーザルでは、専門的知見を有するアドバイザーとの質疑応答や外部有識者を含む審査委員による審査などを経て、最優秀提案者を選定しており、手続に問題はないと考えております。また、同プロポーザルは、提案自体を選ぶコンペ方式と異なり、あくまで提案者を選ぶものであり、提案内容についても双方の協議により変更を行う場合があることを募集要項に明記していたものであります。今後のプロポーザル実施に当たっても、これまで同様に適正な手続を経て事業者を選定してまいります。
次に、3の新スタジアムについての(1)民設民営の可能性と3分の2の公費負担と、(2)の八橋運動公園への整備と、(3)の維持管理に係る赤字負担について、一括してお答えいたします。
新スタジアムについては、これまで民設民営を想定し、ブラウブリッツ秋田が中心となって設立するスタジアム整備会社を事業主体として検討を進めてきております。現在、ブラウブリッツ秋田及び県、市による新スタジアム整備協議会において、官民連携による事業手法も含め、様々な議論をしているところであり、御質問の内容につきましては、今後の3者協議の中で、適宜、精査及び検討を行っていくことになるものと考えております。
次に、4の子どもたちの笑顔が輝く秋田市への(1)少子化対策につながる本市の取組についてであります。本市ではこれまでも、産業の振興と安定した質の高い雇用の創出に取り組むとともに、仕事と子育ての両立ができる社会づくりを推進するなど、子どもを生み育てやすい社会づくりにつながる施策に取り組んでまいりました。これまでの取組を踏まえ、今年度は、庁内連絡協議会においてライフステージに応じた本市の支援策を整理し、若い世代のニーズとの整合を検証して、より効果的な支援策となるよう取り組んでまいります。
○議長(菅原琢哉) 卸売市場再整備担当部長。
【鷲谷達夫 卸売市場再整備担当部長 登壇】
◎卸売市場再整備担当部長(鷲谷達夫) 2の(1)卸売市場の工期等の変更と全体を見直す考えについてお答えいたします。現卸売市場は、開場から約50年が経過し、経年劣化による建物や設備の老朽化が進行しているほか、施設の構造が開放型で、現代の流通形態や社会的ニーズへの対応が困難な状況にあることから、早期の再整備が必要と捉えております。卸売市場の再整備に当たっては、令和5年3月に策定した卸売市場再整備基本構想において、費用や期間の面でメリットの大きい現市場用地での建て替えとしたものであり、また、工期短縮は事業費の縮減にもつながることから、整備地やスケジュール等の見直しは考えておりません。
◎教育長(佐藤孝哉) 4の(2)本市学校教育の評価についてお答えいたします。本市では、子どもたちに自立と共生の力を育むことが大切であるとの考えに立ち、豊かな人間性をはじめ、確かな学力や健やかな体をバランスよく育む学校教育を推進しております。各種調査の結果から、本市においては、将来の夢や目標を持ち、人や社会の役に立ちたいと考えている子どもが多く、各校において、子どもが自らの生き方を考えるキャリア教育や、人と人との絆のすばらしさを実感する体験活動などの充実が図られているものと捉えております。
次に、(3)の子どもの事故対策についてであります。本市では、魔の7歳と言われる小学校1年生が交通事故に遭うことのないよう、入学時に黄色い帽子を無償配布しているほか、交通安全教室を実施し、安全な横断歩道の渡り方など、基本的な交通ルールを指導しております。また、事故防止対策として、見守り隊による通学路での安全指導や、中学生の自転車通学でのヘルメット着用の徹底などに取り組んでおります。通学の安全確保に向けては、交通安全上の危険箇所を減らすことが課題と捉えており、警察、道路管理者、学校、教育委員会等による合同点検により、今後も安全対策の推進に努めてまいります。
次に、(4)の小・中学校における窒息事故対策と救急車の到着時間の把握、窒息事故対応の実技訓練についてであります。本年2月に福岡県で発生した窒息事故を受け、本市では、事故の可能性のある食材の使用を中止するとともに、児童生徒への食べ方指導や事故発生時の対処法について研修を実施しております。また、救急車の到着時間を正確に把握してはおりませんが、各校ごとに危機管理マニュアル等を作成し、事故発生時の対応について共通理解を図るとともに、外部講師を招いた救命救急講習会を開催しております。今後も、教職員一人一人が窒息事故の正しい対処法を身につけることができるよう、関係機関と連携して取り組んでまいります。
次に、8の安全安心な暮らしに向けての(1)北朝鮮による拉致問題についてのア、映画「めぐみへの誓い」の活用状況と、拉致問題に関する学習についてであります。拉致問題については、中学校社会科の学習で取り上げており、拉致問題がいまだ解決していないことや、我が国が一刻も早い解決を目指していることなどを指導しております。本年2月に寄贈されたDVDについては、教材の一つとして各校において活用が図られていくものと考えております。
次に、(3)の熊対策のうち、登下校時における児童生徒の安全確保策についてであります。学校周辺に熊が出没した場合には、速やかに警察、農地森林整備課、教育委員会で情報を共有し、学校を通じて保護者へ注意喚起のメール配信を行うほか、送迎の要請や教職員の巡回など、適宜対応しております。また、新たに、市立小・中学校の全児童生徒に熊よけ鈴を貸与するとともに、市立小・中・高等学校等に熊撃退用スプレーを配布することとしており、引き続き、登下校時の安全確保に努めてまいります。
○議長(菅原琢哉) 子ども未来部長。
【斉藤聡美 子ども未来部長 登壇】
◎子ども未来部長(斉藤聡美) 4の(4)子どもの窒息事故対策と救急車の到着時間の把握、窒息事故対応の実技訓練のうち、幼稚園・保育園分についてお答えいたします。窒息事故対策としては、国の事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン等を各施設に周知し、窒息につながりやすい食材などについて注意喚起をしております。救急車の到着時間は把握しておりませんが、各施設において窒息事故対応を含めた実技講習を定期的に実施していることを確認しております。今後も、保育現場を訪問した際には必要に応じて指導し、事故の未然防止に努めてまいります。
次に、(6)の子どもの一時預かり等についてであります。一時預かりなどの利用は、保育の安全を確保するため、職員配置や利用人数により受入れ可能かを判断することから、施設へ事前に申し込むこととなっております。施設によっては、定員に余裕がある場合など当日の受入れを可能とする柔軟な対応をしていただいているところもありますが、全ての施設に同様の対応を求めることは困難と考えております。
次に、(7)のうち、保育士等を対象とする奨学金返還助成事業の継続と対象施設の拡充についてであります。本事業は、保育人材を確保し待機児童の解消を図るために実施しているものであり、令和4年度に一度募集期間を延長し、待機児童がほぼ解消されたところでありますが、再度の延長については、状況を見ながら判断してまいります。なお、本事業は待機児童の解消が主な目的であることから、児童養護施設などを対象施設に加えることは考えておりません。
○議長(菅原琢哉) 消防長。
【渡辺邦博 消防長 登壇】
◎消防長(渡辺邦博) 4の(5)救急搬送を断ったケースはあったのかについてお答えいたします。本市では、救急出動した場合、医療機関に搬送することを前提に活動しており、これまで救急隊から搬送を断った事案はありません。救急隊員の小児に関する研修受講状況は、秋田県メディカルコントロール協議会が推奨する教育コースや、医療機関が開催する研修会を受講しております。
○議長(菅原琢哉) 保健所長。
【伊藤善信 保健所長 登壇】
◎保健所長(伊藤善信) 4の(7)のうち、看護師等を対象とする奨学金返還助成事業の継続についてお答えいたします。本事業の実施により、看護師及び准看護師並びに歯科衛生士の就業者数が継続して増加するなど、人材の確保が図られており、一定の事業効果があったものと捉えております。本事業は、令和4年度に一度募集期間を延長したところであり、今後については、状況を見ながら判断してまいります。
次に、8の(2)がん患者へのサポートについてのア、ウイッグ・乳房補正具の購入費用助成についてであります。本市においては、県と市の助成金を合算し、ウイッグについては2万5,000円を、乳房補正具については2万円を上限に交付しているところであります。本市の助成金額は他都市と同程度であることや、申請者の反応を踏まえ、助成金額は妥当なものと捉えております。
次に、イのへアドネーションの促進と、市職員が行う上での課題についてであります。現在、国内で3つの団体が支援活動をしており、寄附された髪を使用して作成したウイッグを希望する患者に無償提供するとともに、提供者の相談にも応じております。今後は、必要に応じて、このような支援団体の取組を患者及びヘアドネーションを希望する方へ情報提供してまいります。また、市職員がヘアドネーションを行うことについては、職員個人の意思に委ねられるものであり、市として課題等はないものと認識しております。
○議長(菅原琢哉) 都市整備部長。
【山下浩司 都市整備部長 登壇】
◎都市整備部長(山下浩司) 5の公共交通等についての(1)公共交通への積極的な関与についてのア、都市交通への積極的な関与とバスの利用率が低い理由についてお答えいたします。秋田中央交通が運行する路線バスについては、昨今の運転士不足に加え、労働時間規制などの影響を受け、通勤時間帯における便数の確保を優先するため、夜間の運行を制限せざるを得ない状況となっております。今後、同社と締結した連携協定に基づき、路線バスの確保・維持やバス利用率の向上に努めてまいります。
次に、ウの市営バスの移管に関する現在の評価及び基本協定書を保存していない理由についてであります。公共交通事業については、国においても、これまでの事業者による競争が利用者の利益につながるという方針から、共同経営の導入など事業者同士が連携して地域の公共交通を守るという方針に変わっているほか、営業所設備の集約など、本市全体のバス事業として効率化も図られたことから、民間への移管については適切であったと考えております。また、基本協定書が保存されていないことについては、秋田市文書取扱規程に基づく保存期間が満了したことからであります。
次に、エの共同経営体の検討状況と幹線バス路線の一部公営化、旧80条バスの運行についてであります。公共交通における共同経営体の実現については、交通事業者を取り巻く環境や経営状況等の変化も踏まえ、共同経営体の設立ではなく、バス路線網の再編や新たな運賃、支援制度など、経営に関わる事項について本市も積極的に関与するため、今年4月に秋田中央交通と持続可能な公共交通サービスの実現に向けた連携協定を締結したものであります。また、市内のバス交通については、市街地は民間事業者、郊外部は本市が実質的な事業主体としてマイタウン・バスを運行しておりますが、現状においては、乗合運送の免許を保有し、路線バス等を担える民間事業者がいるほか、セーフティーネットとして幹線バス路線など必要な路線を維持するとともに、エリア交通の拡大により対応していくこととしていることから、公営化や旧道路運送法80条に基づく自家用有償運送を本市が行う考えはありません。
次に、オの鉄軌道系の公共交通の整備とLRVの混走についてであります。自動運転の導入については、運転士不足に対応する一つの手法として捉えておりますが、新たな鉄軌道系の公共交通については、運行空間の確保や費用面などの問題があることから、整備は考えておりません。また、JR線路におけるLRVの混走及び踏切ごとの停留所の設置については、既存のJR線に与える影響が大きいほか、踏切での安全確保に支障が生じる可能性が高いことから考えておりません。
次に、カのタクシー事業者に対する運賃割引分への補助についてであります。一般的なタクシー移動については、乗合交通と異なり、個別の移動手段であるほか、運転免許返納者に対して割引などのサービスを実施している他の事業者との公平性が保てないため、現時点ではタクシー運賃割引分への補助は考えておりません。
次に、キの交通事業者に対する市職員の派遣及び給与補助などの直接的な支援についてであります。バスやタクシー運転手の給与に対してのみ直接的な支援を行うことは、他の業種との公平性の観点から困難でありますが、運転手の確保につながるものとして、資格取得助成事業では、バスやタクシーの運転に必要な二種免許の取得費用の助成を行っております。また、本市職員を民間へ派遣するには、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に定められた条件を満たす必要があり、人材不足解消のための派遣は困難であります。
次に、(2)のバス路線網の再編及びエリア交通についてのア、バス路線網の再編についてであります。令和6年3月の市議会建設委員会でお示しした再編案については、本市としての考え方を示したものであります。今後、バス事業者が主体となって、既存路線の利用状況や運転手の勤務時間、車両の待機場所などを考慮した具体的な経路の検討を行うこととしており、本市との連携会議などにおいて協議しながら、再編を進めてまいります。
次に、イのエリア交通についてであります。エリア交通については、タクシー運賃と比べ大幅に安い運賃となっていることから、現時点で1日乗車券や回数券を導入する考えはありません。また、エリア交通における交通系ICカードの利用については、既に多くの車両にキャッシュレス決済端末が設置済みとなっておりますので、事業者への補助は考えておりません。
次に、7のまちづくりと地域の活性化についての(1)秋田市立地適正化計画の評価と地域自治区の検討についてであります。同計画は、策定後、おおむね5年ごとに評価することとしており、現在、今年度内の秋田市都市計画審議会への報告に向け、検証・評価を進めているところであります。なお、立地適正化計画で定める事項は、居住や都市機能を誘導する区域のほか、これらを誘導するための施策等であり、地域自治区については検討しておりません。
次に、(2)の仲小路へのアーケード整備に向けての市の関わりについてであります。アーケードについては、既存の大屋根等と同様、地元商店街等が主体となって整備すべきものと捉えておりますが、多額の事業費や歩行者専用道路化への合意形成等、多くの課題が想定されることから、現時点での整備は困難であると考えております。
次に、(3)の中心市街地の低未利用地の暫定利用についてであります。中心市街地では、秋田駅西口駅前広場等での移動販売車の出店など、公共空間を利用した取組が増加してきているところであり、民有地でもこうした取組が行われることは、中心市街地のにぎわいの創出に寄与するものと認識しておりますが、土地所有者との合意形成など課題も多いことから、まずは公共空間の活用による取組を進めながら、にぎわいを波及させるよう努めてまいります。
次に、(5)の中心市街地へのマンション建設時に1階をテナント化する働きかけと、建設地の現状に対する考えについてであります。中心市街地において、連続的に店舗等が立地することは、回遊性や滞在性、商店街の魅力向上につながるものと認識しておりますが、マンション建設は民間事業であり、市が働きかけを行うことは難しいものと考えております。また、テナントがないマンションであっても、まちなか居住の受皿として中心市街地の居住人口が増加することから、地域の活性化に寄与しているものと捉えております。
○議長(菅原琢哉) 環境部長。
【千田佳正 環境部長 登壇】
◎環境部長(千田佳正) 5の(1)のイ、公共交通分担率とカーボンニュートラル実現に向けた交通分野の取組についてお答えいたします。本市は、広く分散した都市構造により、現状では自家用車に頼らざるを得ない地域も少なくないことから、まずは、現在進めているバス路線網の再編やエリア交通の運行区域拡大など、公共交通を利用しやすい環境を整備することが最優先事項であると考えており、公共交通分担率を目標値として定める考えはありません。また、ゼロカーボンシティの実現に向けた交通分野の取組は、自家用車並びにバス及びタクシーへの電気自動車等の導入が考えられますが、価格や冬期間の航続距離などに課題があります。このため、国や自動車業界では、高効率な車載用電池などの技術開発を進めており、これらの動向に注視してまいります。
次に、(3)自家用車等の利用についてのア、急速充電ステーション及び水素ステーションの整備についてであります。急速充電設備は、主に長距離移動での利便性向上を目的に設置されており、限定的かつ短時間の利用となっております。また、市内の民間施設で設置が進んでおり、需要に追いつかない状況には至っていないものと認識しております。そのため、市有施設への設置は、市内の急速充電器の使用や普及状況を踏まえ、必要性を調査してまいります。また、水素ステーションについては、秋田市新エネルギービジョンにおいて、商用車のFCV化等の促進を施策の一つとしていることから、国の支援策も踏まえながら、民間事業者等による交通要所等への水素ステーション設置に対する支援を研究してまいります。
○議長(菅原琢哉) 観光文化スポーツ部長。
【納谷信広 観光文化スポーツ部長 登壇】
◎観光文化スポーツ部長(納谷信広) 5の(3)のイ、道の駅あきた港の駐車場についてお答えいたします。道の駅あきた港は、市が所管する秋田市ポートタワーや秋田港振興センターと、県が管理する駐車場などが一体となった施設であります。そのため、道の駅の運営は県・市が連携して行っており、御提案のありました土地の活用などを含め、必要な課題について、県と協議してまいります。
次に、7の(7)「これが秋田だ!食と芸能大祭典」の評価といつまで開催するのかについてであります。「これが秋田だ!食と芸能大祭典」は、本市並びに全県域への誘客や県内周遊観光の拡充を目的に実施しており、今年は2日間で約14万3,000人の来場者があったことから、中心市街地のにぎわいづくりにも寄与しているものと認識しております。また、県外客拡大への取組が課題である一方、県内各市町村の魅力の再発見や祭り本番への誘客など、域内観光の推進に成果があったものと考えております。来年度以降の開催については、実行委員会を組織している秋田商工会議所や秋田観光コンベンション協会などと協議、検討をしてまいります。
○議長(菅原琢哉) 危機管理監。
【佐々木 毅 危機管理監 登壇】
◎危機管理監(佐々木毅) 6の災害対策・危機管理についての(1)広報監の新設と昨年の大雨災害における情報発信についてお答えいたします。昨年7月の豪雨災害発生以降、市民への各種支援情報の発信や周知については、情報量が多過ぎて見づらいなどの意見がありましたが、その後は掲載方法の改善を図り、既存の組織体制の下、対応できていたものと認識しております。こうしたことから、広報監を置くことは今も考えておりませんが、災害対策本部を設置する規模の災害が発生した場合は、沈静化するまでの間、本部事務局に広報班を設置するなど、引き続き情報発信体制の強化に努めてまいります。
次に、(2)の令和6年能登半島地震を踏まえた対応についてのア、本市からの応援職員の派遣状況及び応援職員によるフィードバックの活用についてであります。本市では、1月10日以降、金沢市や七尾市等へ、避難所での健康管理や応急給水業務、家屋被害認定調査などを行う職員を計42名派遣し、被災地域の早期復旧・復興に向けた支援に努めてきたところであります。また、派遣した職員からの報告を受けて、避難所での感染症予防の手順を見直すほか、他自治体へ応急活動を要請した場合の受援体制について、災害対応訓練で再確認するなど、派遣で得られた知見の活用に努めてまいります。
次に、ウの大規模地震などに対する、本市の防災における弱点とその対策についてであります。本市と能登半島地震の被災地域では、冬期間、厳しい寒さや積雪に見舞われるほか、津波被害が想定される沿岸部に位置する点などが地理的に類似しており、地震災害における弱点であるものと認識しております。これらを踏まえ、今年度は、冬期間における災害の発生や長期化する避難所生活に備えるため、暖房器具や防寒用品などの備蓄品を拡充するほか、各家庭での備えの重要性や津波ハザードマップを活用した避難の心得について、引き続き市民に周知・啓発を図ってまいります。
次に、(3)の自主避難所や在宅避難者に対する物資の提供についてであります。本市では、地域防災計画において、指定避難所以外の町内会館や自宅、自動車などに避難している被災者について、町内会や自主防災組織等の協力を得て状況の把握に努め、必要な食糧・物資を提供することとしております。提供方法については、最寄りの指定避難所での受渡しを基本に、状況に応じて、災害協定に基づき、配送を要請するなど柔軟に対応してまいります。
次に、(4)の屋外スピーカーを備えた防災無線の設置についてであります。他国からの武力攻撃などに関する情報は、Jアラートを通じて、テレビ放送や携帯電話への緊急速報メール、緊急告知ラジオなどで市民に広く伝達されております。屋外スピーカーを備えた防災無線は、配信の多重化を図る手段の一つではありますが、市内全域をカバーする場合、相当数のスピーカーを整備した上で維持管理する必要があり、事業費が多額となることから、整備は困難であると考えております。
○議長(菅原琢哉) 上下水道事業管理者。
【工藤喜根男 上下水道事業管理者 登壇】
◎上下水道事業管理者(工藤喜根男) 6の(2)のイ、耐震管等の継ぎ手被害とその対応についてお答えいたします。能登半島地震の耐震管被害については、大規模な地盤崩落により継ぎ手が離脱したものであり、それらの箇所を除けば耐震管の被害報告はなく、耐震対策の有効性が確認されたところであります。仮に被害が生じた場合は、配水系統間の水融通や応急給水活動、他都市への応援要請により対応してまいります。
次に、8の(4)水道水におけるネオニコチノイド系農薬の対策についてであります。ネオニコチノイド系農薬の検査については、季節変動を踏まえ、今年度5月、8月、11月に実施し、結果を公表することとしております。また、仁井田浄水場等整備事業において粉末活性炭処理設備を整備する予定であり、カビ臭とともに農薬類の除去においても効果が期待できるものと考えております。他自治体との協議についてでありますが、昨年の研究グループによる調査結果によると、農薬使用量の多い時期でも国が定める目標値の200分の1程度であり、農薬使用について協議を行う考えはありません。
○議長(菅原琢哉) 建設部長。
【須磨一郎 建設部長 登壇】
◎建設部長(須磨一郎) 7の(4)呉市と同様に、歩道を公園区域に変更し、屋台を公募する取組を中土橋などで行う考えはないかについてお答えいたします。市道上に屋台を設置するためには、道路占用許可が必要であり、許可に当たり一般交通の支障とならないなど、一定の要件を満たす必要があります。中土橋などでは、イベント開催に合わせて道路利用者の安全を確保した上で、短期間屋台が設置されている事例もあり、にぎわいの創出に一定の効果があるものと捉えておりますが、長期間の屋台の設置は、周辺施設の利用状況などから道路利用者の安全が確保されないため、現状では困難であります。
○議長(菅原琢哉) 市民生活部長。
【柴田 浩 市民生活部長 登壇】
◎市民生活部長(柴田浩) 7の(6)街路樹の管理等についてお答えいたします。街路樹の管理については、市民サービスセンターの担当者会議を行い、仕上がりに地域差が生じないよう情報共有を図ってきたところであり、昨年度からは専門家による講習会を開催し、樹木の生育や景観に配慮した剪定となるよう努めております。また、街路樹の管理の在り方について建設部と協議するとともに、剪定ガイドラインの作成など、今後も適切な管理に取り組んでまいります。
○議長(菅原琢哉) 総務部長。
【佐々木 保 総務部長 登壇】
◎総務部長(佐々木保) 8の(1)のイ、市有施設における特別ライトアップについてお答えいたします。北朝鮮人権侵害問題については、これまで市庁舎へのポスター掲示や展示パネルの設置のほか、映画「めぐみへの誓い」の配信案内などにより周知を図ってきたところであり、今後とも、多くの市民に関心と認識を深めていただけるよう、特別ライトアップも含め、さらなる周知・啓発に努めてまいります。
次に、9の議会への関心を高める取組についての(1)答弁の状況等についてであります。一般質問等で「検討する」との答弁については、現時点においても、様々な観点から施策の実施要否等の判断が必要な場合に用いております。また、検討期間の設定については、社会情勢の動向等を見極める必要があり、実施に向けて取り組むこととした時点で、市議会に対し報告するなど、適時適切な情報提供に努めてまいります。
次に、(2)の議会答弁書の事前配付についてであります。答弁書の事前配付については、現在のところ考えておりません。
○議長(菅原琢哉) 産業振興部長。
【吉田 忍産業振興部長 登壇】
◎産業振興部長(吉田忍) 8の(3)の熊対策のうち、取組と目撃情報の速やかな周知についてお答えいたします。熊対策については、市民への注意喚起を速やかに行うため、目撃情報を基に警察、猟友会及び庁内の関係各課が情報共有し、連携した対応を取るとともに、農作物被害や人身被害を防止するため、箱わなの設置や草木の刈り払いによる緩衝帯の整備などを実施しております。また、今年度は、秋田市公式LINEなどにより熊の出没情報を周知しているほか、新たにAIで熊を判別する自動撮影カメラを導入し、出没情報の多い場所に設置することで、早期発見と迅速な情報提供につなげてまいります。
○議長(菅原琢哉) 福祉保健部長。
【佐々木良幸 福祉保健部長 登壇】
◎福祉保健部長(佐々木良幸) 8の(5)生活保護の障害者加算の認定誤りにおける過支給分の返還と自立更生に資する費用の柔軟な対応についてお答えいたします。生活保護の制度上、実施機関の瑕疵による過支給が生じた場合であっても、そのことを理由に返還を求めないことはできないこととなっております。また、返還額の決定に当たり、領収書などの証拠書類を紛失していても、当該世帯の自立更生のためのやむを得ない用途に充てられたものと認められる費用については控除し、柔軟に対応しております。
再質問
○議長(菅原琢哉) 再質問ございますか。――若松尚利さん。
【6番 若松尚利議員 登壇】
再質問:1-(3) / 他自治体に先駆けた取組と庁内の風潮
◆6番(若松尚利) 答弁ありがとうございました。
それでは、最初に1の(3)についてお伺いいたします。秋田公立美術大学と連携した取組ですとか、あきた芸術劇場ミルハスの件とか、よく分かりました。ただ、私的には少し物足りないと思うところがあります。市長の見た感じというか、それで十分だということなのですけれども、こういう聞き方をしてよいのか分からないですけれども、逆に部長たちからすると、挑戦する風潮があるのかどうかというのは、どのように捉えられているでしょうか。
◎企画財政部長(齋藤一洋) まず、御質問にありましたような先駆的な取組ということでは、市長が答弁したようないろいろな取組、その他もあると思っております。それで、やはり実務的には、一番大事なのは、先駆的ということに合わせて、この秋田市というまちに合わせて、持続可能で継続的な取組も重要だと思っておりますので、そういう形で、やはり今必要なものと、それから将来的に必要なものという観点を加えて、行政経営会議などで新規の事業なども総合的に判断させていただいておりますので、そういう意味合いでは、議員の皆様からの意見も含めて、職員のアイデアも含めて、均等にそういった形で判断をしていると捉えております。
再質問:1-(4) / 市長が実現したいと強く思っていること
◆6番(若松尚利) ありがとうございます。
次に、1の(4)に行きます。まあ1の(4)に限った話ではないのですけれども、市長が今力を入れていらっしゃる外旭川地区のまちづくりにおいて、先ほどの答弁の中にもありましたが、人口減少下でも持続可能なまちづくり云々という話をよくされると思いますが、事業パートナーに頼った計画なわけですから、一企業によるものなので、例えば人口減少で経営状況とか事業計画が一企業の判断で変わる可能性がもちろんあるわけですから、それが果たして持続可能と言えるのかなということに少し疑問に思うのですけれども、その辺いかがでしょうか。
◎企画財政部長(齋藤一洋) 外旭川のモデル地区整備に当たりましては、やはり持続可能な社会基盤の構築という観点ですので、官民連携のモデルをやはり念頭に置いております。ですので、事業パートナーは、構想、それから計画をつくる段階で、いろいろなノウハウを提供いただいておりまして、市の考えに合わせた計画をつくっておりますが、実際、仮にまずこのまま我々のほうでいろいろと検討しまして、地域未来投資促進法など実現に至った場合には、その中で、事業パートナーにかかわらず、いろいろな民間の事業者が官民連携の取組に賛同していただければという前提で考えておりますので、そういった形で、一社にとらわれない、一社に頼ることのない、そういった持続可能な基盤につなげられればと思っております。
再質問:1-(5) / 万博に対する本市の考え方
◆6番(若松尚利) ありがとうございます。
次は、1の(5)に行きたいと思います。単純に、この加盟を考えていないということだったのですけれども、メッセージ性としては、秋田市の市長は万博に協力しないと捉えられてしまうと思うのですけれども、その認識で間違ってないでしょうか。
◎企画財政部長(齋藤一洋) 答弁させていただいたように、加入している、していないにかかわらず、万博という国のイベントということでは協力をさせていただきたいという視点に変わりはございません。
◆6番(若松尚利) その東北絆まつりで竿燈が行くというのはよく分かったのですけれども、ほかの展示などの機会もやはりある――本来であればあるはずなのですが、やはりそういうところにも参加してないというところを考えると、やはり秋田市は万博に協力的ではないと捉えられてしまうと思うのですけれども、これ、何かやはり入りたくない事情があるものでしょうか。
◎観光文化スポーツ部長(納谷信広) 東北絆まつりとしての参加でありますが、これは、これまで東北6市で積み重ねてきた絆まつりの中でも一大トピックになると思います。非常に大きな事業だと、関係6市、準備に向けて非常に頑張らなければいけないなという決意を固めているところであります。このような形で参加するということ自体が、万博を応援するという形になると思いますので、東北の力で万博を盛り上げていきたいと考えております。
◆6番(若松尚利) 大変しつこくて申し訳ないのですけれども、盛岡市や山形市、青森市、県内でもかなりの市が加入しているこの首長連合に入らないというのは、やはり市長的に万博は何かいまひとつだなと思っているところがあるものでしょうか。
◎企画財政部長(齋藤一洋) 今、事例でお話がありましたように、東北の県庁所在地の中でも加入、未加入というのは分かれておりますが、それぞれの都市も実際一切協力しないということではなくて、逆に、どちらかというと、先ほどお話があったように絆まつりでは一体となって協力したいという姿勢でございますので、そういった特に他意はございません。
再質問:2-(1) / 卸売市場の工期等の変更と全体を見直す考え
◆6番(若松尚利) できれば加盟を引き続き検討していただきたいと思うのですが、2の(1)に行きます。今、卸売市場再整備担当部長のほうから答弁をいただいたのですが、市場のほうはもちろん市場の事業者向けに、一刻も早く市場を建て直したいとか、そういった事情は分かるのですけれども、この聞き方も少しあれなのですが、これ、外旭川地区のまちづくり的には割と悪くない考え方だと思うのですけれども、逆に、まちづくりのほうとしてはどのような受け止めになりますか。
◎企画財政部長(齋藤一洋) 市場と、それからスタジアムと民間施設の3つを、相乗効果を出すような形でモデル地区にしたいということで検討を進めてまいりました。今、御提案があった内容も確かに一つの選択肢というのは御理解いたしますが、これまでの検討の経過で、例えばスタジアムについては、ブラウブリッツと県と協議会をもって場所を合意してきたり、それから、市場については、先ほど申し上げたように関係者の意向を踏まえて、やはり市として、市場は都市機能として必要だという観点からやったりということで、それらをその段階ごとにきちんと決定してきておりますので、今時点、ここでは、まずは提案のような見直しをする考えはないということでございます。
◆6番(若松尚利) 答弁しにくいですし、多分されることではないのかもしれないですけれども、今時点で考えていないということであれば、このままだと進まなそうだなということであれば、この私が例に出したものに限らず、割と大きめにまちづくりに関して考え方を変えるという可能性があるということでよろしいでしょうか。
◎企画財政部長(齋藤一洋) 人口減少下においての持続可能な社会基盤の構築と、それから交流人口の拡大による新たな活力・魅力の創出という、そういう大きい目的は変わっておりませんので、それに基づいて検討はしたいと思っております。ただ、いずれいろいろな関係機関とか、関係者からの御意見もいただいておりますので――いわゆる県やブラウブリッツ、Jリーグなどからの御意見もありますので、そういったものを含めてしっかり検討していきたいということでございます。
○議長(菅原琢哉) 若松尚利さん。
再質問:2-(3) / まちづくり事業パートナー選定プロポーザル
◆6番(若松尚利) 2の(3)に行きます。手続上に瑕疵があるということは、もちろん私も思っておりません。ただ、結果的に、この提案内容で決めたというよりは事業者を選ぶプロポーザルだったということではありますが、結果的にやはりほかの提案者の案にだんだん近づいていってるわけです。提案者3のほうが、もともとスタジアムを市場のほうに置いていたりなどしているわけで、もちろん事業者を選びたいのだというプロポーザルは分かるのですけれども、やはり後から見ると、何だったのだろうなと思う人も多いと思うので、これからプロポーザルの募集要項とか募集条件、今後生かせる教訓がないかなというのを聞きたくて、こういう質問をこの項目の最後に聞かせてもらったのですけれども、何か得られる教訓はありますでしょうか。
◎企画財政部長(齋藤一洋) まず御指摘のあった点につきましては、評価の項目が当然ありましたので、募集、提案いただいた三者からの評価をしっかりしたということでございます。ですので、募集要項にも、協議の上で内容を変更する可能性があるというのは明記して、それを理解していただいた上で手を挙げていただいておりますので、結果、その提案の内容に近づいたとかそういうことではなくて、あくまでもプロポーザルの段階では、次点の業者であっても、例えばスケジュール感であったり、同時に市場とスタジアムを整備できるかという点においては、やはり課題のある提案だったということは、ホームページの概要版だけで分からないところはあるかとは思います。そういう意味では、しっかりと評価項目を準備しまして、外部委員を入れて審査していただいておりますので、まずこの案件を踏まえて見直すなど、そういう形は特に必要はないと考えております。
再質問:3-(1) / スタジアム 民設民営の可能性と3分の2の公費負担
◆6番(若松尚利) 3の(1)に行きたいと思います。後段の、ほかの民間施設整備を行う際に云々というところについて答えてもらってないような気がするので、お答えいただければと思います。
◎企画財政部長(齋藤一洋) やはりこの場合は、県と市でお話ししているスタジアム、それから、一つの例としては、県・市連携文化施設のあきた芸術劇場ミルハスのような共同で整備するものもある。そういうその時々でやはり関わり方や、それから公共性の有し方など、そういう意味合いで負担の割合というのも変わってくると思いますので――必要性の判断と負担の割合も変わってくると思いますので、一概にはお答えしかねるというところであります。
◆6番(若松尚利) そうすると、ある程度公共性があると思われるものであれば、今後も、整備費の3分の2くらいを公費で負担したものでも、民間のものですよというものが出てくる可能性があるということでよいのでしょうか。
◎企画財政部長(齋藤一洋) 例えば、組合の再開発事業とかそういったものについても、負担する例というのはございますので、そういう意味合いでは、3分の2ということは、特にこの場では全然こだわりはないですけれども、必要に応じた割合とかそういったものは、その事業の性質によって検討されていくものと考えております。
再質問:3-(2) / スタジアム 八橋運動公園への整備
◆6番(若松尚利) 3の(2)なのですけれども、これもまた後段のほうをきちんと答えてもらってないような気がするので、もし八橋地区でスタジアムを整備するとなったときに、どういう課題があって、その解決策として考えられるものが何かということを教えていただきたいです。
◎企画財政部長(齋藤一洋) まずは、八橋地区という仮定の話でございまして、これからブラウブリッツと県との新スタジアム整備協議会で、その方向でよろしいかどうかという合意を取って検討していくものでございますので、その段階で、やはり具体の課題、それから前回の検証との違いというのをしっかりと確認していくものと思いますので、今の段階で細かくというものはないと思います。
◆6番(若松尚利) 少し聞き方を変えると、今の段階で八橋地区に持ってくるというのは、その協議の内容次第では、特に何の問題もない、課題もないということでよろしいのでしょうか。
◎企画財政部長(齋藤一洋) どういう課題を検討していくべきかという、今の社会情勢や、Jリーグの基準の変更もありましたけれども、そういったものも含めて、どういう課題をしっかりやっていくかというのを三者で共有した上で進めていくべきものと思っております。
◆6番(若松尚利) 私たちは、スタジアムを造るに当たって、ここがよいであろうと場所を決めた後に、ここは少し地盤が駄目なのではないのという話になって、ひっくり返ったのを我々は見てるわけです。それで、仮にブラウブリッツと県と市の協議で八橋地区にスタジアムを持ってこれます、持ってきましょうとなったときに、いや、実はここ、地下に何かが埋まっていて造れないですよとか、あるいは、昨日の御答弁でもあったような公園の面積であるとか、施設の面積であるとか、あるいは八橋運動公園や第2球技場の利用率の問題だとか、何かそういった課題が出てくるのではないかなと。後から出てくるくらいだったら、今のうちに課題をピックアップしていただいて、先に解決策を考えていただいたほうが、前のようなことにならなくて済むと思うのですけれども、いかがでしょうか。
◎企画財政部長(齋藤一洋) そうした課題を三者で共有して、八橋地区も選択肢の一つになり得るかという検討をするのがこれからだと思っております。
◆6番(若松尚利) しつこいようですけれども、では、そういう課題はないのですか。特に地下に何かが埋まっていて造れないだとか、面積的にも絶対無理だということがないということでよいのでしょうか。
◎企画財政部長(齋藤一洋) そういった課題が、まずあり得るかどうか。それから、どういう検討をしなければいけないのかということを、これから三者でやはりピックアップしていくという段階だと思います。
再質問:4-(3) / 子どもの事故対策
◆6番(若松尚利) 4の(3)なのですけれども、御説明いただいて、すごく秋田市の事故対策というか、そういったものはよく分かったのですけれども、最後のところで、やはり実施に向けた課題とその解決策について聞いているのですが、例えばヘルメットを配ったりとか、ライフジャケットを各学校に持っていったりするに当たって、何か課題があるものでしょうか。
◎教育長(佐藤孝哉) ヘルメットを配ることだとかライフジャケットを配ること自体の課題は、特にございません。ただ、先ほどお話のあった小学校1年生に黄色いヘルメットを登校時にかぶらせるといったことの事例に関して申し上げますと、小学校1年生という発達段階の子どもが歩行時にヘルメットをかぶるといったものが、使用性としていかがなのかといったことは、私は課題があると考えております。
◆6番(若松尚利) 自転車用の子どもさんのヘルメットはいかがでしょうか。
◎教育長(佐藤孝哉) 先ほどお答えしたように、通学時の中学生の自転車通学に関しましては、ヘルメットの着用率が100%でございます。また、通学以外の自転車利用の際のヘルメットに関しましては、それは推奨されておりますので、保護者の判断で十分その着用をしていただきたいなと考えているところであります。
再質問:4-(4) / 子どもの窒息事故対応の実技訓練
◆6番(若松尚利) 続いて(4)なのですけれども、外部講師を呼んで講座を開催しているというお話だったのですが、それを受講してるのは担任の先生やいわゆる保育園で一緒にいる先生など、そういう方なのでしょうか。
◎教育長(佐藤孝哉) 学校に関して申し上げますと、救命救急講習会を受講しているのは教職員であります。
再質問:4-(7) / 保育士等を対象とする奨学金返還助成事業の継続と拡充
◆6番(若松尚利) 次、4の(7)です。答弁される部署が多岐にわたっていて大変申し訳ないのですが、単純にこれを今年でやめますよということになると、単純に事業の目的などは分かるのですが、去年の人たちは補助してもらったのに、私たちはしてもらえないという不公平感みたいなものが生じるのではないかなと思うのですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
◎子ども未来部長(斉藤聡美) 現在募集に当たりましては、申請期間の終了時を明示しておりますので、現段階において、そこのところは周知を図っているところであります。
再質問:5-(1)ア / 都市交通への積極的な関与とバスの利用率が低い理由
◆6番(若松尚利) 5の(1)のアに行きます。バスの不便さというところで、いろいろ事情は分かりました。一方で、私も、福島市みたいに頑張って22時台の運行をしているところもあるということを踏まえつつ、逆に、飲食店や、それこそコンサートなど、そういった興行面、文化振興面においても、やはりこの辺、大事なところだと思うのですけれども、交通分野以外のところで、バスをもう少し遅くまで走らせたらどうだみたいなところというのは、庁内で考えられないものでしょうか。
◎都市整備部長(山下浩司) 先ほど答弁で申しましたとおり、今、経営支援といいますか、運転手を通勤・通学の時間に注力するため、昨今、労働時間の規制なども始まりまして、インターバルを必ず9時間置かなければいけないことになっております。そうした意味で、運転手の数が増えてきて、その余裕が出てきましたら、そうしたことも考えられると思うのですが、まずは今必要だというところに注力したいと考えております。
再質問:5-(1)イ/ 公共交通分担率とカーボンニュートラル実現に向けた交通分野の取組
◆6番(若松尚利) 次に、5の(1)のイですけれども、これはやはり公共交通分担率に限った話ではないのですが、2050年にゼロカーボンシティとうたっている以上は、やはり数値目標は、何年度までにこれくらいなどというのがないと、やはり進んでいかないと思うのですけれども、もちろん公共交通分担率をなるべく上げてほしいのはやまやまなのですが、ほかの分野でも数値目標というのは全くないものなのでしょうか。
◎環境部長(千田佳正) 失礼ですが、ほかの分野といいますと、秋田市地球温暖化対策実行計画の中のほかの分野という観点でございますか。――ほかの分野でいきますと、例えば、環境学習におきましては、どのくらいというような数値目標はございますが、交通分野におきましては、分担率に関して数値目標等はしていないということになります。
◆6番(若松尚利) そのゼロカーボンシティの実現に向けて、ほかの分野では何となく数値目標みたいなものがあるのだとすれば、交通面でもやはりあったほうがよいのではないかなと単純に思うのですけれども、それはつくれないものですか。
◎都市整備部長(山下浩司) 公共交通分担率というお話をいただいたのですが、議員も御承知だと思いますが、こちらはパーソントリップ調査といいまして、大変手間と時間とお金のかかる調査でございます。本市を含む区域でも昭和54年にフルスペックで行って、その後、平成17年に簡易的な調査を行ってということでございます。そうした中で数値というのは出てくるわけでございますが、一番直近と申しますか、そのときで、路線バスと、それから鉄道を合わせまして大体4%、自動車交通というのが72%と、そうしたくらいの割合でございまして、仮に路線バスとか鉄道の目標を数%上げましょうという目標をつくったとしても、やはり答弁で申し上げましたとおり、マイカーの利用というのは、ある程度この地方都市では前提にしなければ、大都市圏のように公共交通をこれだけ上げましょうということは、もちろん私たちも目標にしているわけではございますけれども、数値としてお示しするのは困難ではないかと考えております。
再質問:5-(1)ウ / 市営バスの移管に関する現在の評価及び基本協定書を保存していない理由
◆6番(若松尚利) 次に、5の(1)のウなのですけれども、理由は分かりました。保存期間だというのは分かったのですけれども、ただ、現実として、移管されたバスは走り続けていて、秋田中央交通は移管された土地に車庫を構えているわけですから、この最初の協定が今確認できないというのは、少しいかがなものかなと思うのですが、そのあたり受け止めはどうですか。
◎都市整備部長(山下浩司) 保存年限自体は適正に守られていると思うのですけれども、恐らく基本協定書に書かれた内容を自然に考えますと、移管するのですから、秋田市で行っていたようなサービスをある程度頑張って維持してくださいという内容は、恐らく書かれていたと想像されます。そのため、段階的に移行いたしまして、平成17年度に秋田市でバス交通を廃止したわけでございますけれども、現在も継続して関わりを持っておりますし、秋田中央交通のほうでも、路線廃止するときには道路運送法に基づいた手続も必要でございます。その中で、秋田市地域公共交通協議会と、私たち行政のほうですとか、関係機関、それから住民の団体の方々などが入った仕組みの中で、そういった廃止をしておりますので、まずはその辺も適正に行われていると考えております。
再質問:5-(2)イ / エリア交通
◆6番(若松尚利) 次に、5の(2)のイに行きます。先ほど御答弁の中で、タクシーよりエリア交通は安いのだという話をされたのですけれども、比較対象がタクシーというのがすごく疑問に思うのですが、いかがでしょうか。
◎都市整備部長(山下浩司) エリア交通と今は申し上げておりますが、私たち、最初、導入の検討段階ではエリアタクシーという呼び方をしておりました。これを改めましたのは、やはり個別の交通でありますタクシーと、それから小さな公共交通だという意味合いでのエリア交通と分けて考えたいということで、そのようにしたものでございます。ですから、タクシーと比較というお話なのですけれども、例えば個人のお客さん、今までどおりの感覚で、乗合停車所ではなくて自宅から例えば秋田駅に行ったり、また、スーパーや病院等というのは、個別交通の考え方と考えております。それで、乗換え拠点、タクシーなどでスーパーのほうにも直に行くように、このエリア交通というのはいろいろルートは用意しておるのですけれども、そこで差がつくものと考えております。
◆6番(若松尚利) 最初は何とかタクシーということだったかもしれないですけれども、バス路線の再編も踏まえて、エリア交通があるから、この辺、バス路線、日中走らなくてもよいみたいな話も今出てきているわけです。そうなると、やはり比較対象はタクシーであったら駄目で、普通の乗合バスであったりとか、場合によってはシニアアキカを使った料金であるべきだと思うのですけれども、そこを踏まえて、やはり高い、高いですよ。利用しにくいと思うのですけれども、いかがですか。
◎都市整備部長(山下浩司) そうした受け止め方もあるかもしれないのですけれども、バスに比べて目的地等にも近づいて行きやすいということもございますので、高過ぎるという考えは今のところ持っておりません。
◆6番(若松尚利) しつこくて申し訳ないのですが、バスも選べる、エリア交通も選べるということであれば、便利になってるから少し高いというのはもちろん理論として分かるのですけれども、バスが選べなくなった状態で高い。シニアアキカの人と比べると劇的に高い。これ、やはり少しおかしくないでしょうか。
◎都市整備部長(山下浩司) 今御利用なられている方々からも、御利用に関していろいろな御意見というのは、今現在、あまりそういった御意見というのは来ておりませんが、今後もそうした御意見、私たちも大変そうした御意見も集めまして、使いやすい、それから、そうした割合で分担率の適正化、そうしたところを検討していきたいと考えております。
◆6番(若松尚利) しつこくて申し訳ないのですけれども、今、現にバスはまだ走っているわけなので、御意見はまだ出ないですよね。だからそれはきちんと考えてもらわないと困るわけで、ぜひ、シニアアキカを使えるように、あるいは回数券、そういったものを使えるように検討していただきたいですが、いかがでしょうか。
◎都市整備部長(山下浩司) エリア交通は、これからも順次エリアを拡大していきますけれども、その内容については、これで決まりということではございませんので、それが値下げの方向になるかということは申し上げられませんけれども、今後、また使いやすいように検討してまいりたいと思っております。
再質問:5-(3)ア / 急速充電ステーション及び水素ステーションの整備
◆6番(若松尚利) 5の(3)のアです。急速充電器の必要性の調査と、水素ステーションの研究をされるということだったのですけれども、いつ頃までされる予定でしょうか。
◎新エネルギー産業推進担当部長(新出康史) 私のほうからは、水素ステーション設置に対する支援と研究について、期限というお話でしたけれども、現段階で、民間事業者の方が水素ステーション設置に対する具体的な事業を行っているという具体的な事例は、まだございません。こうした動きが出た際にしっかり対応できるように、関連の制度を調査、これから研究していくということでございますので、その調査・研究の期限というのは、そうした実際に事業者の動きが出てくる時期になろうかと思います。
再質問:6-(4) / 屋外スピーカーを備えた防災無線の設置
◆6番(若松尚利) 6の(4)ですが、後段の国などの補助金を活用できないですかという質問にお答えしてもらってない気がするので、お答えをお願いいたします。
◎危機管理監(佐々木毅) 先ほどの答弁において、事業費が多額となるということで整備は困難であると考えていると申し上げました。ですので、国などの補助金の活用というのは、それも考えていないということにはなるのですが、仮に整備をするとしても、県の総合防災課のほう、あるいは過去に整備をしたこと、実績のある自治体のほうなどに確認をしたところ、国のこの屋外スピーカー、防災無線の増強といいますか、拡充に対しての補助金メニューはないというふうに伺っております。また、起債の借入れ、こちらは国の緊急防災・減災事業債というメニュー、起債のメニューがございますので、そちらの活用は可能と見込まれますが、こちらは借入れは100%可能ですが、交付税措置、後年度の元利償還金に対しての交付税措置については、7割交付される、算定されることになっておりますが、残りの3割については持ち出しというような制度でございます。
再質問:7-(2) / 仲小路へのアーケード整備に向けての市の関わり
◆6番(若松尚利) 7の(2)です。仲小路のアーケードなのですが、多額の事業費だというのはもちろん分かるのですけれども、課題として交通量みたいなこともおっしゃられていたのですが、エリアなかいちによって仲小路が分断されたことにより、現在、仲小路はそんなに車走っているのかなと思うのですけれども、仲小路の自動車の通行量と、全国で全蓋式アーケードの中で、時間帯であったり、時間帯に限らず車が通れるところもあると思うのですが、そういったところとの比較を考えて、そんなに困難な理由になるものなのでしょうか。
◎都市整備部長(山下浩司) 先ほど答弁で申し上げましたのが、歩行者専用道路化とすることがアーケードの基本でございます。――全蓋式アーケードの場合ですが。そうした場合、議員が今お話しになられましたとおり、商店街ですと、どうしても荷入れ、荷さばきといったことが必要になりますので、午前中の例えば朝10時までは、そうした関係車両だけの通行は許すとか、そうしたこともございます。ただ、基本的に日中それ以降の時間は、地元の人であっても車の出し入れはできないといった事例が多くございます。そうした中で見ますと、今の仲小路の中で日常的に出入りしている事業者がいますと、まずは少しその点で難しいのではないかということでございます。
◆6番(若松尚利) 私もデータを持っているわけではないので申し訳ないのですけれども、仲小路の東西方向の交通が止まっていることによって困るところは、言うほどないように見えます。意外と細い道もあるので、南北方向の道である程度、それこそアトリオンの駐車場の出入りなど、解決してしまうわけですから、時間帯を区切って、全蓋式アーケードの中でも車が通れないこともないのではないかなと思うのですけれども、何かそういった調査とか行ってみる気はないですか。
◎都市整備部長(山下浩司) 調査ということであれば、昨年度、中核市、あとは仙台市とかを対象に、アーケードの整備に関して、どの程度行政のほうで関与しているかとか、大規模修繕も行ったのかとか、そうした私たちも興味のあることをアンケート調査させていただきました。その中で、やはり全く行政のほうで主体となっているところというのがございませんで、一方で、民間のほうでまとまって整備するときに、補助金という形で関与しているところはございます。現在ある大屋根も、地元の方から御要望がありまして、私たちのほうも補助金という形で対応させていただいております。今、アーケードがない部分につきましても、まず地元の方々がそこに全蓋式のアーケードを欲しいのか、そうした声というのは私たちのほうでもまだ聞いておりませんけれども、そうしたことで御相談、どうして進めていったらよいのかということであれば、当然私たち行政ですので、相談にも応じさせていただきたいと思います。
◆6番(若松尚利) 多分、その地元の商店街は、金銭的な負担があるのだったら要らないという話になりがちだと思うのですけれども、秋田市として、エリアなかいちまでの観光客の動線を、雨や雪に濡れないようにという考え方もあると思うのですけれども、秋田市としては、あそこは要らないという考え方ですか。あればあったほうがよいななのですか。どのようなものですか。
◎都市整備部長(山下浩司) あちらの道路については、融雪も入れさせていただいておりますし――広小路もそうですけれども、そうした意味では、当然雨が降れば傘は必要ですが、それなりに快適に歩いていただけるという空間だと思います。それから、最初あそこは、歩車共存道路ということで大変全国でも先駆けて、そうした、コミュニティー道路と申し上げましたけれども、そうしたことで始めた道でございます。ですから、そのときからぶれてはいないということ――少し申し上げにくいのですが、歩行者と車が、道路のスピードが落ちるようにジグザグにもなっておりますし、通りにくい道ではないと考えております。
再質問:7-(4) / 呉市と同様に、歩道を公園区域に変更し、屋台を公募する取組を中土橋などで行う考えはないか
◆6番(若松尚利) 全国に先駆けての取組でやった道路ということであれば、アーケードの面でも全国に先駆けて取り組んでいただきたいなと思います。7の(4)に移ります。困難な理由をいろいろ御説明いただいたのですけれども、その困難な理由を越えるために、呉市では歩道の一部を公園指定したということだと思うのですけれども、全く難しいというお考えですか。
◎建設部長(須磨一郎) 中土橋、あるいは広小路など、現在の施設の利用状況、あるいは道路の利用状況からして、短期間であればイベント開催時に車両を規制して対応するというのは、にぎわい創出につながるよい取組だと思っておりますけれども、長期間にわたってその道路を規制するというのは、現実的に考えて困難であるということでございます。
再質問:8-(2)イ / へアドネーションの促進と、市職員が行う上での課題について
◆6番(若松尚利) 8の(2)のイなのですけれども、現実的に髪の長い男性職員が受付――少し言い方がよくないのかな、男性職員が受付にいると、やはり市民の皆さん、何だこりゃと思うことがあると思うのですけれども、そういうアンコンシャス・バイアスというのですか、そういったものがあったら駄目だと思うのですけれども、例えばバッジをつけて、私は今、ヘアドネーションをやっていますよなどというようなものがもしあれば、これ全国に先駆けた取組になって、先ほど1の(3)のところで言った、全国に先駆けた取組になるような気がするのですが、そういったことを考えられないものでしょうか。
◎総務部長(佐々木保) ヘアドネーションにかかわらず、市の職員のそういった服装に関してのお問合せというのは多々あるかと思います。そういった場合には、しっかり説明をして理解を求めたいと思っておりますし、場合によっては、そういったことについても検討していきたいなと思います。
再質問:8-(3) / 熊対策
◆6番(若松尚利) 8の(3)のドローンの部分、消防のほうとか、どのような感じですか。
◎消防長(渡辺邦博) 消防で活用するドローンにつきましては、あくまでも災害用ドローンということでございますので、事故現場や火災現場など人命検索、それから火災現場における災害状況の実態把握、こういったものに活用・運用しているところであります。熊対策に例えますと、被害があったということであれば、その被害状況の確認ですとか、隊員の二次災害防止のための安全確保などについて活用することが想定されております。ただ、このような状況でありますので、熊のみを探すということについては、現在想定しておりません。
再質問:8-(5) / 生活保護の障害者加算の認定誤りにおける過支給分の返還と自立更生に資する費用の柔軟な対応
◆6番(若松尚利) 8の(5)です。生活保護を受けている方が返済義務を負うということは、事実上、生活保護の額が減らされて、罰を受けているというと少し言い過ぎかもしれませんが、減額されてしまうように見える形になるのですけれども、それ悪いのは受給者ではないというところで、やはりこれ、返さなければいけないものなのでしょうか。
◎福祉保健部長(佐々木良幸) 先ほどの答弁でも述べましたけれども、生活保護の制度上、実施機関の瑕疵による過支給が生じた場合であっても、そのことを理由に返還を求めないことはできないこととなっております。ただ、そうした中、返還額の決定に当たりましては、例えば領収書がなくても、自立更生費用として認められるものにつきましては認めるような柔軟な対応をしております。
再質問:9-(2) / 議会答弁書の事前配付
◆6番(若松尚利) 最後にします。9の(2)なのですけれども、私、さっきから何回か再質問の中で、後段答えてもらってませんとか、この部分答えてもらってませんというのを何回か言っているのですけれども、これ、私、皆さんが答弁してるのを一生懸命メモしてるから気づくのですけれども、やはり当日の朝でもよいので答弁書をいただければ、あらかじめ、ここ、後段答えてもらってないやなど分かるのですけれども、これ難しいものですか。
◎総務部長(佐々木保) 答弁書の事前配付につきましては、まず議会の運営に関することでありますので、慎重に取り扱う必要があると考えてございます。現在は、当局としましては、分かりやすく、かつ簡潔に答弁することを心がけておりますので、現在の時点では、当局側から配付することは考えてございません。
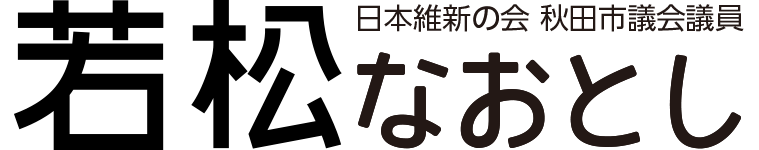









コメント